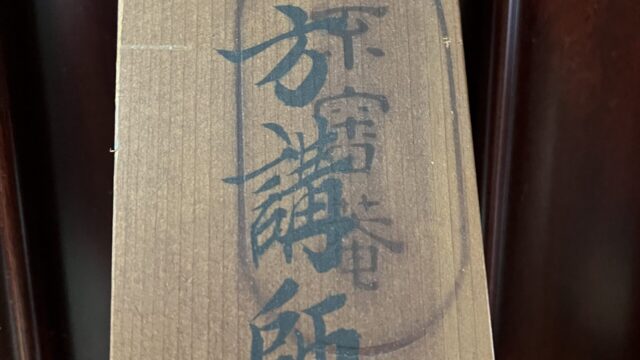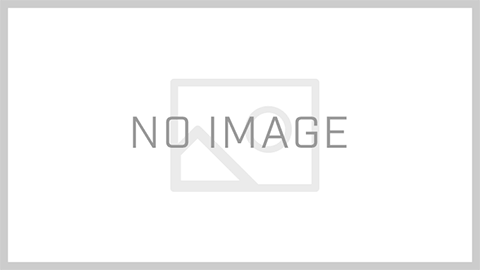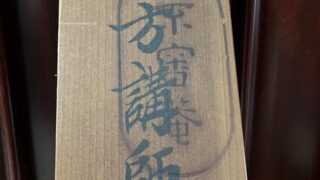Contents
- 1 茶花図鑑
- 1.1 茶花ルール・茶花禁
- 1.1.1 1月の茶花は柳
- 1.1.2 利休の好まなかった花の一つに木瓜(ボケ)があります。 長持ちする花でとげが付いているためか、とげを落とせばよいという話もありますが、利休は好みませんでした。
- 1.1.3 2月の茶花は黄水仙
- 1.1.4 3月の茶花は菜の花
- 1.1.5 4月茶花は牡丹
- 1.1.6 5月の茶花は花菖蒲
- 1.1.7 『 6月の茶花は 笹百合 』です。
- 1.1.8 朝茶の風情を楽しむ季節です。
- 1.1.9 8月の茶花は浜昼顔
- 1.1.10 茶花の種類は夏らしい品種が並びます。
- 1.1.11 9月茶花は白木槿
- 1.1.12 10月の茶花は嵯峨菊
- 1.1.13 十月で風炉は終わり、茶席では(名残の茶事)を大切にします。
- 1.1.14 11月の茶花は磯菊
- 1.2 茶の湯の正月と言われる11月です。
- 1.3 茶道の花の生け方のルール
- 1.4 まとめ
- 1.1 茶花ルール・茶花禁
茶花図鑑
茶花とは「茶室の床に生ける花」の事を言います。
野草を生ける自然で素朴な花を生けるのが茶花の理想形です。庭に生えた草花を摘み、季節に合わせて、お花が茶席に彩を添えます。
この画像は、道端に咲いた草花を摘んできて、野の花をなげ生けた画像です。
茶花は本来こうした野の花を生けるものなんです。
この記事では、野花をはじめ、茶道で使える茶花を「月別」にご紹介していきす。
お茶室では茶花はなくてなならない大切な存在なんです。
茶花ルール・茶花禁
「茶花の季節12か月」
茶道では季節、毎の花を大切にします。
1年を二つに「 炉 と 風炉 の時期 」に分けた季節の茶花を生けていきます。 画像の茶花は近所の道端で咲いていた野の花です。
画像の茶花は近所の道端で咲いていた野の花です。
可憐で夜になると花はつぼみ、朝になると再び満開になります。
茶道では『季節を11月~4月』までを、『炉の季節』と言って、
茶室に炭火の温度が回るように部屋『茶室』を暖めます。
『畳に炉を』切って、使います。
『5月~10月』までを、『風炉の季節』と言って、季節が暖かくなってきて
茶室の温度が上がらないように『風炉釜を』据えて、炭火の温度が茶室にいきわたらないように間口をせばめた風呂釜を使用します。
この様に『寒い時期と暖かくなる時期を一年を二つ』に使い分けるのです。
炉の季節=「寒い季節」
風炉の季節=「暖かい季節」
茶花の十二か月は季節の変化に応じながら、月毎の花に季節感を出して、
生けていきます。(投げ入れ)
春夏秋冬それぞれの季節で使われる野の花植物がありますので、月別に茶花を下記に詳しく説明しましたので見ていきましょう。
1月の茶花は柳
正月の茶花は一本の長い柳の枝を一つに結んで生けます。
結び柳を床柱に流麗にお正月は床に飾られることが多いです。
竹の二重切の花入れに(上の窓に柳 )下の窓に( 椿 )を生けます。
1月の茶花は柳と椿が定番になっていますが、更に曙椿(アケボノツバキ)と鶯神楽(ウグイスカグラ)もお正月に相応しい茶花なので、生けてみました。
鶯神楽は赤い小さな花をつける枝ものです。
この枝を使って、曙椿を竹の一重切りの花入れに生けると、茶室に春が訪れたようになりました。
茶事の初座で掛けられていた掛物を外した後、床の正面には花入れが飾られる方飾り、初座と後座に掛物と花入れを別々に飾り替えることで、それぞれの掛物や花入れがより鮮明に客人の心に伝わります。
利休の好まなかった花の一つに木瓜(ボケ)があります。 長持ちする花でとげが付いているためか、とげを落とせばよいという話もありますが、利休は好みませんでした。
茶花の種類は、白梅(ハクバイ)、椿(ツバキ)、土佐水木(トサミズキ)、白玉椿(シラタマツバキ)、千両(センリョウ)、川柳(センリュウ)、セツブンソウ、紅梅(コウバイ)、白侘助椿(シロワビスケツバキ)、雪中花椿(セッチュウカツバキ)、曙椿(アケボノツバキ)、山茱萸(サンシュユ)と共に
🔶「炉の季節」には欠かせない茶花になっています。
2月の茶花は黄水仙
2月の茶花は黄水仙です。
黄水仙は投げ入れにしてみました。
黄水仙は(キスイセン)は一種飾りで、すっと伸びた葉を5本投げ入れにしてみました。
細くて長い葉がキスイセンの花を引き立てています。
黄水仙の特徴は花の中心に口を開けた筒状の花びらが1枚ついている
カップ状の「副花冠」があります。
「副花冠」のなかには1本の雌蕊と6本の雄蕊 が付いています。
黄水仙(キスイセン)は葉がイグサのように細く、イトズイセンとも呼ばれ、香りが強く、匂い水仙ともいわれています。 春を待ちわびる気持ちは茶席の花にもこたえた黄色の水仙が華やかで清々しいです。
茶花の種類は侘助椿(ワビスケツバキ)白梅(ハクバイ)金花茶(キンカチャ)初雪草(ハツユキソウ)山椿(ヤマツバキ)福貴草(フッキソウ)曙椿(アケボノツバキ)虫狩(ムスカリ)水仙(スイセン)などがあります。
3月の茶花は菜の花
3月の茶花は菜の花です。
菜の花は十字形に黄色い4枚の花びらを咲かせて、ボリュウムがあり華やかなので、備前の花入れに一種で生けてみました。
菜の花の花の特徴は黄色い4枚の花びらが十字形に咲いていています。
3月になるとあちこちで咲いているのを見かけます。
茶室に春の到来ですね!
🔶🔶3月は利休忌「家元行事」千利休の命日です。🔶🔶
この日、表千家では家元が利休ゆかりの「菜の花」や「白木蓮」の花などを供えて
利休をしのびます。
花見月の花を生ける、春の訪れを身近に感じる季節です。
『茶花の種類』 は侘助椿(ワビスケツバキ)、山査子(サンザシ)、土佐水木(トサミズキ)、虫狩(ムスカリ、紫蘭(シラン)、赤侘助椿(アカワビスケ)、貝母(カイボ)、白木蓮(シロモクレン)、山吹(ヤマブキ)、袖隠し椿(ソデカクシツバキ)、木瓜(ボケ)、庭桜(ニワサクラ)、藪椿(ヤブツバキ)、十五倍子(キブシ)など芽吹きの枝ものや野の花を生けたり、3月は啓蟄、冬こもりの虫たちが一斉に顔を出してきます。
茶花で春の訪れを感じる月ですね。
4月茶花は牡丹
4月の茶花は牡丹です。
牡丹は花と葉が大きいので、花の大きさに合わせて葉を切り取り、新芽の出た木を添えて、生けました。
4月、5月の春から初夏にかけて咲く牡丹は春牡丹と呼ばれ、寒牡丹に比べて
花と葉が大きいです。
牡丹(ボタン)、雪笹(ユキササ)、大葉紅柏(オバベニカシワ)、 射干(シャガ)、翁草(オキナクサ)、金花茶(キンカチャ)、都忘れ(ミヤコワスレ)伊予(イヨミズキ)、司うつぎ(ツカサウズギ)ほうちゃく草(ホウチャクソウ)、西洋南天(セイヨウナンテン)、源平桃(ゲンペイモモ)など春は他にもいろんなお花の種類があります.
『牡丹』は花の王者と言われる。
牡丹は茶の湯で珍重される花の一つです。
5月の茶花は花菖蒲
薫風さわやかな新緑の季節、5月は茶席の「炉」を閉じて「風炉」の茶室にかわります。
「茶花」や「お道具」も変わり「 琉球風炉 」を使い「 初風炉の季節 」の行事は「端午の節句」です。
茶花は端午の節句には欠かせない花菖蒲(ハナショウブ)。

茶花の種類は花菖蒲(ハナショウブ)、 鉄線 縞葦 (テッセンシマアシ)、下野 姫小百合(シモツケ・ヒメサユリ)、 梅花空木 縞葦 (バイカウツギシマアシ)、肝木 縞葦(カンボクシマアシ)、 大山蓮華 (オオヤマレンゲ)など茶花は新緑の季節にふさわしく色んな種類を楽しめます。

『 6月の茶花は 笹百合 』です。
笹百合は大輪の花1本を籠に生けます。
笹百合は淡い桃色から白色の花を咲かせる日本特産のユリです。
葉が笹に似ていることから笹百合と名が付きました。
淡い桃色に白の花を咲かせ、葉は披針形で、互い違いに生える 葉の質は
やや厚く葉は笹に似ています。
笹百合は野山に自然に咲く花です。
細い茎の割りに大ぶりの花を咲かせるのが特徴です。
『 茶花の種類 』は、笹百合(ササユリ)、京鹿子縞葦(キョウカノコ シマアシ)、穂咲七竈 縞葦 (ホサキナナカマド シマアシ)、玉川杜鵑草(タマガワホトトギス)、半夏生(ハンゲショウ)、下野(シモツケ)昼咲月見草(ヒルサキツキミソウ)、矢筈薄(ヤハズススキ)節黒仙(フシグロセン)などがあります。
『 茶花の種類 』は京鹿子 縞葦(キョウカノコ シマアシ)、穂咲七竈 縞葦 (ホサキナナカマド シマアシ)、玉川杜鵑草(タマガワホトトギス)、笹百合(ササユリ)、半夏生(ハンゲショウ)、下野(シモツケ)、昼咲月見草(ヒルサキツキミソウ)、矢筈薄(ヤハズススキ)、節黒仙(フシグロセン)などがあります。
この中で矢筈薄(ヤハズススキ)が私は大好きです。
半夏生(ハゲッショウ)、昼咲月見草(ヒルサキツキミソウ)、下野(シモツケ) などと一緒に生けると夏を感じてきますね。

この画像は庭につぼみをつけたアジサイの画像です。
『 7月の茶花 』は 朝顔
暑さを避けて、早朝の涼味が一番の幸せです。 風炉の季節を代表する花の白木槿(シロムクゲ)は、朝花開くので、明け方に
開いたばかりの枝を切り、たっぷりの水につけておき『花の命』を生かします。
朝茶の風情を楽しむ季節です。
『 茶花の種類 』は:白木槿 (シロムクゲ)、岨菜(ソバナ)、 白木槿白蓼 、(シロムクゲ シロタデ)、 歌仙草 唐松草 (カセンソウ カラマツソウ)、白木槿 松明草 (シロムクゲ タイマツソウ)、白桔梗 矢筈薄 (シロキキョウヤハズススキ)、底紅木槿 (ソコベニムクゲ)、秋海どう (シュウカイドウ)、待宵草 (マチヨイクサ)、昼咲月見草 (ヒルサキツキミソウ)、雌待宵草 (メマツヨイクサ )、赤祇園守 (アカギオンマモリ)、紫詰草 (ムラサキツメクサ)、酔芙蓉 (スイフヨウ)、朝顔(アサガオ)、檜扇(ヒオウギ)などの茶花があります。
8月の茶花は浜昼顔
『八月の茶花』は:葉月(ハズキ)、桂月(ケイズキ)、観月(カンゲツ)、八月八日頃には立秋になります。
茶花の種類は夏らしい品種が並びます。
風船葛(フウセンカズラ)、浜昼顔(ハマヒルガオ)、昼顔(ヒルガオ)、檜扇(ヒオウギ)、蓮(ハス)、桔梗(キキョウ)、岩煙草(イワタバコ)、薄雪草(ウスユキソウ)、姫海芋(ヒメカイウ)、河骨(コウホネ)、鋸草(ノコギリソウ)、糸薄(イトススキ)、河原撫子(カワラナデシコ)、現の証拠(ゲンノショウコ)、大文字草(ダイモンジソウ)、仙人草(センニンソウ)など種類があります。
9月茶花は白木槿
白木槿(シロムクゲ)、金水引(キンミズヒキ)、丸葉藍(マルハアイ)、吾亦紅(ワレモコウ)、矢筈薄(ヤハズススキ)9月の茶花で吾亦紅に矢筈薄この取り合わせが好きです。
残暑のなかに季節の移ろいが感じられる月です。白木槿(シロムクゲ)や底紅木槿(ソコベニムクゲ)も盛りを終えて小さくなり、秋の野花や糸薄(イトウス)の登場が茶席に秋の気配を感じさせます。
茶花の種類は:徐々に秋らしくなってきました。
秋明菊(シュウメイキク)、白杜鵑草(シロホトトギス)、下野(シモツケ)、吾亦紅(ワレモコウ)、糸薄(イトススキ)、刈萱(カルカヤ)、黄花秋桐(キバナアキギリ)、霜柱(シモバシラ)、白萩(シラハギ)、丸葉藍(マルハアイ)、矢筈薄(ヤハズススキ)、田村草(タムラソウ)などの茶花があります。
10月の茶花は嵯峨菊
上臈杜鵑草(ジョウロウホトトギス)、嵯峨菊(サガキク)、吾亦紅(ワレモコウ)の秋草に晩秋の野の風情を感じます。
十月で風炉は終わり、茶席では(名残の茶事)を大切にします。
『茶花の種類』は:豊富です。嵯峨菊(サガキク)、杜鵑草(ホトトギス)、吾亦紅(ワレモコウ)、薄(ススキ)、紺菊(コンギク)、吹上菊(フキアゲギク)、野路菊(ノジキク)、水引(ミズヒキ)、紫式部(ムラサキシキブ)、土佐水木(トサミズキ)、丸葉の木(マルハノキ)、弁慶草(ベンケイソウ)、梅鉢草(ウメバチソウ)、関谷の秋丁字(セキヤノアキチョウジ)、薙刀香(ナギナタコウ)、釣舟草(ツリフネソウ)、沢桔梗(サワキキョウ)、霜柱(シモハシラ)、萩(ハギ)、数珠玉(ジュジュダマ)、弁慶草(ベンケイソウ)、小紫(コシバ)、紫式部(ムラサキシキブ)、白式部(シロシキブ)、紺菊(コンギク)など、
『 茶花に心が和む10月の花々 』です。
🔶秋草に変わって、茶席には椿が登場します.
茶花の種類は:初嵐椿(ハツアラシツバキ)加茂本弥椿(カモホンナミツバキ)、曙椿(アケボノツバキ)、白玉椿(シラタマツバキ)、西王母椿(サイオウボツバキ)など
冬の足音を聞きながら残り少ない『秋の風情』を楽しみます。
薄茶席には嵯峨菊(サガキク)と杜鵑草(ホトトギス)薄(ススキ)を入れた備前の花入れで、床を飾りました。
風情があってよい取り合わせの茶花ですね!
11月の茶花は磯菊
茶壷の封を切り半年間使ってきた『 風炉釜 』の代わりに『 炉を開き 』、新茶を納めた
『 茶壷の封切り 』茶壷の封切りになります。
茶の湯の正月と言われる11月です。
季節感を何よりも大切にする茶の湯では炉の季節に入ると冬の季節の花が姿を現します。磯菊が盛りと花を咲かせ深まる秋を感じさせます。
『 茶花の種類 』は 初嵐(ハツアラシ)、曙(アケボノ)、アイリス、りょうぶ、蔓梅(ツルウメ)、赤姫椿(アカヒメツバキ)、白椿(シロツバキ)、返り花(カエリハナ)花の種類が少なくなる時期にあって、冬咲きの椿は開花の時を待ってつぼみにもつやのある濃緑色の葉っぱにも輝きが感じられます。
12月の茶花は加茂本阿弥椿
『 冬の茶花 』は 初嵐椿(ハツアラシツバキ)、花水木(ハナミズキ)、更紗灯台(サラサドウダン)、黒文字(クロモジ)、山城菊(ヤマシロキク)、満作(マンサク)、板谷楓(イタヤカエデ)、西王母椿(セイオウボツバキ)、蝋梅(ロウバイ)、加茂本阿弥椿(カモホンアミツバキ)などの茶花があります。
『 茶花の種類 』は:寒蘭(カンラン)、薩摩野菊(サツマノギク)、小浜菊(コハマギク)、秋風楽(アキフウラク)、白八朔(シロハッサク)、大白玉(オオシラタマ)、日本水仙(ニホンスイセン)、楓(カエデ)、房咲水仙(フサザキスイセン)、磯菊(イソギク)の花々です。
茶道の花の生け方のルール
ルール1投げ入れ
茶花は投げ入れが原則です。
自生した野の花を投げ入れで生けるのが基本です。
素朴な佇まいであることが茶道ではよいとされています。
野の花を摘み花瓶に花を投げ入れでいけます。
ルール2禁花
禁花とはお茶席にはふさわしくない花のことです。
香りが強い花やとげのある花、棘や毒のある花は好ましくないとされています。
🔶派手で華美な花、沈丁花(チンチョウゲ)、金銭花(キンセンカ)、柘榴(ザクロ)、河骨(コウホネ)、鶏頭(ケイトウ)などの花が禁花に当てはまります。
ルール3.花入れを場所に合わせて選ぶ置く場所
茶席で飾る花入れには、竹、籐などを編んだ花入れを花籠と呼びます。
唐物、和物に分類され🔶床柱や床の間の壁にある中釘掛けの掛けに置いて使う花入れ『置き花入れ 』🔶壁にかける『掛け花入』🔶天井から花鎖に吊るして使う『つり花入れ』置く場所によって4種類に分けられます。
花入れにはさまざまな種類がありますが、主に「飾り方」と材質によって区分する
『格』で分けることができます。
『飾り方で選ぶ』茶道において花は置いて飾るだけではなく、壁に掛けて飾ったり、
吊るして飾ったりします。
それぞれの飾り方に相応しい花入れがありますので下記に紹介していきます。
『置き花入れ』
床に置く飾り方に用いられる花入れです。
床が畳敷きの場合は置き花入れの下に薄板を敷き、籠で飾る場合は薄板を敷きません。
後述する格によって板の種類も変わります。
『掛け花入れ』
中釘や床柱の花釘に掛ける飾り方に用いられる花入れです。
竹や籠で作られた花入れが『掛け花入れ』として使用されることが多いです。
『吊り花入れ』
床の天井などに花蛭釘に鎖や紐を通し飾る方法に用いられる花入れです。
船の形や月を象ったものが使用されることもあります。
『格で選ぶ花入れ』
格とは茶道で格式を分ける考え方で「真」「行」「草」の三つに格分けがされています。
「真」が最も格が高く、「行」、「草」と続きます。
花入れの材質や形によって格が分けられており、格によって花入れの下に敷く薄板も異なりますので格ごとの花入れを揃えている方もいます。
🔶「真」
「真」は最も格式が高いです。
仏様へお花を供える際に使った花瓶が花入れの始まりと言われています。
茶道が大成するまではそうした花入れには唐物や青磁などが流行し、それらが花入れとして使われておりました。
唐物全盛の頃のものは真に格が分けられています。
例えば、唐銅、青銅、唐物青磁、染付などです。
花入れの下の薄板には真塗の矢筈板を使用します。
🔶花入れには床の間に置いて使う花入れと、床柱や床の間の壁にある中釘掛ける掛け花入れ、床の間の天井から、花鎖に吊るして使う釣り花入れ、置く場所によって4種類に分類することができます。
花入れの選び方
1.金物の花入れ:古桐、唐桐、砂張、モール。
2.焼き物の花入れ:青磁、白磁、染付、陶器。
3.竹の花入れ:一重切、尺八、二重切、三重切、置筒、舟。
4. 籠の花入れ:置き籠、床柱掛けの籠。
茶花に欠かせないのが花入れです。
さまざまな種類がありますが、主に「飾り方」と 材質によって格付されることがあります。
花入れの「挌」を詳しくみると、
🔶真の花入:唐銅の花入、青磁、染付、祥瑞、赤絵、交趾があり、畳床には真塗の矢筈板を使います。
🔶行の花入:釉薬のかかった、瀬戸、丹波、膳所、高取、などがあります。
🔶草の花入:釉薬なしで、畳床には真塗、溜塗、掻合、春慶の塗り物の蛤端の薄板を使用します。
🔶草の花入:備前、伊賀、信楽の釉薬のかかっていないもの、竹、籠の花入などがこれに当たります。
畳床には木地の蛤端の薄板を使いますが、籠花入には薄板は使用しません。
🔶🔶茶花は奇数の本数で生けます。
まとめ
花は生きています。
野の花が愛らしく、道端に咲く野の花に興味を抱くようになり、画像は近所の道端で見つけた可憐な野の花です。
こんなにも野の花が美しいことに気付かせてくれました。
普段何気なく通っている道端に咲く野の花、生命力があり可憐です。
一輪の花をいかに生かすかに心を働かせることが大切です。
茶花は季節だけでなく、生ける人の心を映します。
四季折々に野の花を生けて、花の生命力をいただきます。
美しい花の命を生かすよう、つねに心すること、それが千利休の残した
「花は野にあるように」という教えにあると思いました。