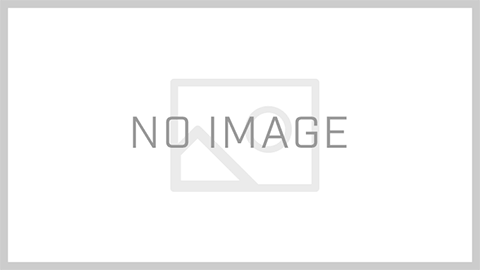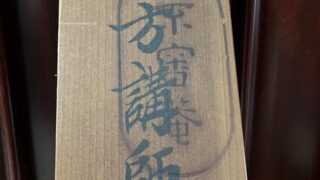Contents
炉初炭点前
炭点前には、(炉の炭点前、炉を切って炭を組む点前)と( 風炉を据えて、炭点前の二通りのお作法があります。
それぞれ、季節によって変えるお作法です。
風炉炭点前 は 季節が暖かい時期に使います。
道安風炉、鬼面風炉、などを使用します。
ここでは炉の炭点前を見ていきましょう。
炭点前をはじめる前に茶道では「お茶を点てる前に必要な炭点前」があります。
炭で湯を沸かしお茶を点てるための大事な炭点前を始める前に炉初炭点前とは、炉の中に新しい炭を組むお点前の事
では 炉初炭点前 を始めましょう
水屋で紙釜敷を懐中し、灰さじを持って入室します。
勝手付き斜めに座り、灰器を置きます。
正面に向き直り、羽箒で初裁きをします。
灰さじで灰を掘り、炭斗で炭を入れます。
火箸で炭を整え、鐶を立てかけます。
羽箒と灰さじを戻し、紙釜敷を出します。
茶会当日は寄付に集ります。
寄付は、待合ともいいます。
待合では足袋を替えるなど手荷物を預けておきます.白湯などを頂きます。
外腰掛、外腰掛に座る客、蹲踞の水をあらためる亭主、客
が揃うと、案内をうけて露地に出て腰掛に進み、腰掛の下座に円座が重ねられ上に煙草盆が置かれているので、次客と詰が腰掛の円座を配り、煙草を正客の脇に置き、客一同円座に座り、亭主の迎え付けを待ちます。
亭主は、座掃にて席中を清め、最後に音をたてて出入口から掃き出し、次に水を張った倶利桶を持って露地に下り、蹲踞の上水を汲み出し、蹲踞の周りを濡らしてから柄杓の柄を清め、倶利桶の水を音を立てて、蹲踞から溢れるように注ぎ、倶利桶を戻したあと中門に向います。
客は、亭主の姿が見えたら腰掛を立ち中門のほうに進みます。
亭主は、門を開いて亭主石の上に立ち、中門を挟んで、主客がつくばって無言の一礼をし挨拶を交わします。
黙礼後、亭主は手がかりを残して閉め、客はその場で亭主が席のほうに戻る後姿を見送り、いったん腰掛に戻ります。
亭主が最後に露地や席中をあらためる時間を少し取ります。
蹲踞をつかう客の頃合いを見計らって、正客から順に蹲踞に進み右手で柄杓に手水鉢の水をたっぷり汲み柄杓半分の水で左手を清め、持ちかえて残りの水で右手を清め、再び右手に柄杓を持ちかえ水を汲み左手に水を受け、手に受けた水で口をすすぎ、最後に残った水を静かに柄杓を立て流しながら柄杓の柄を清め、元に戻します。
お詰は、客一同が腰掛から立つと、円座と煙草盆を元あったように戻し、蹲踞を使う前に中門を閉めます。
蹲踞で手水をつかったら、茶席の出入り口へ進み、手がかりが切ってある戸に手をかけ開け、扇子を前において軽く頭を下げ、席中をうかがい、床、点前座の位置を見定め、にじって席に入り、草履の裏を合わせ、壁と沓脱石の間に立てかけ、席入りします。
床前に進み、掛物を拝見し、続いて茶道口近くの踏込み畳まで進んでから道具畳に進み、器物の飾附と釜と爐とを拝見して、正客は次客以下の席入の妨げとならない場所(仮座)に着きます。
次客は、正客が仮座に着いたら、軽く一礼してにじり入り、草履を同様に扱ってから座して正客に一礼し、正客の通り拝見し、正客の下座へ順に座ります。
お詰は先客が床を拝見し立ち上がったときににじり入り、沓脱石の上の自分の草履の向きを置き変え、出入り口の戸を軽く音をたてて閉め、全員の席入りが終ったことを亭主に知らせます。
お詰が床を拝見し立ち上がったころ、正客は仮座から本来の座に着き、次客以下同様にし、お詰は拝見が終わったら本座に着きます。
客一同が席に着くと、亭主が茶道口を開け挨拶に出ます。
挨拶が終わると、正客より掛物等について尋ね、掛物等についての問答があります。
裏千家 炉 炭点前
亭主が茶道口を開け、炭道具を持って出て、炭道具を炉の隣に置きつけます。
つぎに釜の鐶付に鐶を掛けて、釜を持ち上げ、釜敷の上に置き、羽箒で、炉縁と炉壇の上を掃き清めます。
ここで、正客は挨拶をして、炉の近くに進み出ます。
次客以下も同様にして、客一同が炉を囲むような形で座り炭点前の拝見をします亭主が(ぬれ灰)をまき、羽箒で(五徳の爪)と(炉縁と炉壇)の上を掃き清めたあと、炭をつぎます。
炭がつぎ終わるとお詰から順に席に戻り正客だけが残ります。
表千家 盆香合 炉
亭主は香合を取り香を置きます。
正客は、亭主が(香合)の蓋をするころ、(香合の拝見)のあいさつをします。
亭主は、あいさつを受けて香合を出し釜の鐶付に鐶を掛けて、釜を持ち上げ、
五徳の上に置きます。
正客は釜が掛かったら香合を持って席に戻り畳の縁外、上座寄りに置きます。
正客から炭道具についてあいさつがあり亭主はそれに答えて炭道具を持って
茶道口から退出します。
亭主が茶道口を閉めると正客は上座に預かっていた香合を取り、香合を次客との間に置いて挨拶をしてから膝前に取り拝見します。
次客以下も同様に拝見します。
お詰の拝見が終わると、(香合)を持って立ち上がり、道具畳近くで
正客と出会い、正客に香合を返して席に戻ります。
正客は、もういちど検める気持ちで香合を拝見してから香合を戻します。
亭主が、(香合を)とりに出たら、正客は礼を述べ席入り香合について問答をします。
問答が終わると、亭主は香合を持って、茶道口に帰ります。
中立
客人が菓子を頂き、お詰(末客)が菓子器を給仕口へ返すと、正客は床前へ進み床を拝見し次は道具畳に進み、名残の拝見をしてから出入り口を開けて、自分の立てかけて置いた履物を揃えて露路へ出ます。
次客以下も順に同様にし、お詰は席中に取り残された者がないか見て露路へ出ます、
出入り口の(戸を少し音の)するように閉め切り、亭主に退出したことを知らせます。
亭主は、出入り口の戸を閉めきる音を聞いて給仕口を開け、菓子器を取り込み掛物を外し、釜の蓋をして、席中を掃き清め、花入を掛けて花を入れ、水指や茶入を置き付け、釜の蓋を切ります。
客は腰掛に戻り円座を配り各自手洗いを済ませて休憩します。
亭主は準備が整ったら銅鑼を「大小大小中中大」と七点打ち、客に準備が整ったことを知らせます。
この時亭主が銅鑼の代わりに迎えるときもあります。
客は銅鑼の音が聞えたら少し前に進み出て、つくばって銅鑼の音を聞きます。
「銅鑼の余韻」が聞えなくなると、客はいったん腰掛に戻り、正客から順に蹲踞に進み、
右手で柄杓に手水鉢の水をたっぷり汲み、柄杓半分の水で左手を清め、持ちかえて残りの水で右手を清め、再び右手に柄杓を持ちかえ、水を汲み左手に水を受け、手に受けた水で口をすすぎ、最後に残った水を静かに柄杓を立て流しながら柄杓の柄を清め、元に戻します。
お詰は客一同が腰掛から立つと、円座と(煙草盆)を元にあったように戻し蹲踞を使う前に中門を閉めます。
蹲踞で手水をつかったら茶席の出入り口へ進み、手がかりが切ってある戸に手をかけ開け、扇子を前において軽く頭を下げ席中をうかがい、にじって席に入り、草履の裏を合わせ壁と沓脱石の間に立てかけ、席入りします。
正客は床前に進み(花入と花)を拝見し続いて茶道口近くの踏込み畳まで進んでから道具畳に進み、(器物の飾附)と(釜と爐と)を拝見して、正客は次客以下の席入の妨げとならない場所(仮座)に着きます。
次客は、正客が仮座に着いたら、軽く一礼してにじり入り、草履を同様に扱ってから座して正客に一礼し、正客の通り拝見し、正客の下座へ順々に座ります。
お詰(末客)は、先客が床を拝見し立ち上がったときににじり入り、沓脱石の上の自分の草履の向きを置き変え、出入り口の戸を軽く音をたてて閉め、全員の席入りが終ったことを亭主に知らせます。
亭主は、出入り口の戸を閉めきる音を聞いて、露地に下り、蹲踞の水を入れ替え、円座、煙草盆を引き、窓の簾を外します。
4種類の炭点前
炭点前には
1.初炭点前、
2.後炭点前、
3.炉炭点前、
4.風炉炭点前の
4種類 の 炭点前 があります。
(お道具)と(お点前)はそれぞれ異なります。
炭点前の道具
1.風炉用の炭
風炉は火を入れて釜をかけ湯を沸かすのに使う道具です。
5月から10月の間は(風炉)が据えられこの期間を(風炉の時期)と言います。
風炉用の(くぬぎ炭)は 炉用の(炭よりサイズは小さい炭)になります。
2.炉 用の炭
炉用 の炭 は 茶席で湯を沸かすのに用いる囲炉裏の略です。
11月~4月は炉を用いるのがこの時期で、(炉の季節)になります。
風炉用のくぬぎ炭よりサイズが大きく、使う炭の数も多くなります。
初炭に使うお道具
1.炭斗(すみとり)
2.炭は9本と白枝炭
3.羽箒(はぼうき)
4.れるお道具は火箸(ひばし)
5.鐶(かん)
6.紙釜敷(かましき)
7.香合(こうごう)です。
炭の種類
胴炭は最も大きく最初に据える芯となる炭です。
1.丸毬打(マルギッチョ)胴炭に比べて細く、長さも半分。
3.丸管炭は胴炭に比べて細いが、同じ長さは割管炭は管炭を縦半分に割ったものです。
4.点炭は一番最後に入れる炭です。
5.白枝炭は細い枝の白色の炭です。
炭点前 は 炭をくべて湯を沸かす点前です。
炭点前の所作 は 茶道そのもの、美しく流れがあって
絶やしたくない お炭点前 です。
時代の流れで、(炭を使う点前)は徐々に少なくなり、正式な茶事 以外は
電熱器 で応用することが多くなってきました。
炉の炭点前 は拝見するだけで風情 があり茶道には欠かせないものですが、
電熱器を代用するように変化しています。
( 炭点前 )が続けられるように(炭屋さん)を絶やさないこと。
現実には文化生活が進み、炭屋さんとしての存続が課題になってきました。
「席入り」
炭で湯を沸かしお茶を点てるための大事な炭点前を
始める前に席入の説明を見ていきましょう。
1.席入
2.茶会当日は寄付に集ります。
3.待合では足袋を替えるなど手荷物を預けておきます.
白湯などを頂きます。
4.外腰掛、外腰掛に座る客
5.蹲踞の水をあらためる亭主
6.客が揃うと、案内をうけて露地に出て腰掛に進み、腰掛の下座に
円座が重ねられ上に煙草盆が置かれているので、次客とお詰が腰掛の円座
を配ります。
7.煙草を正客の脇に置き、客一同円座に座り、亭主の迎え付けを待ちます。
8亭主は、座掃にて席中を清め、最後に音をたてて出入口から掃きだし、
9.次に水を張った倶利桶を持って露地に下り、蹲踞の上水を汲み出し、蹲踞の
周りを濡らしてから柄杓の柄を清め、倶利桶の水を音を立てて蹲踞から溢れるように注ぎ、倶利桶を戻したあと中門に向います。
10.客は、亭主の姿が見えたら腰掛を立ち中門のほうに進みます。
11.亭主は、門を開いて亭主石の上に立ち、中門を挟んで、主客がつくばって無言の一礼をし挨拶を交わします。
12.黙礼後、亭主は手がかりを残して閉め、客はその場で亭主が席のほうに戻る後姿を見送り、いったん腰掛に戻ります。
亭主が最後に露地や席中をあらためる時間を少し取ります。
(10)頃合いを見計らって、正客から順に蹲踞に進み右手で柄杓に手水鉢の水をたっぷり汲み柄杓半分の水で左手を清め、持ちかえて残りの水で右手を清め、再び右手に柄杓を持ちかえ水を汲み左手に水を受け、手に受けた水で口をすすぎ、最後に残った水を静かに柄杓を立て流しながら柄杓の柄を清め、元に戻します.
(11).お詰は、客一同が腰掛から立つと、円座と煙草盆を元あったように戻し、蹲踞を使う前に中門を閉めます.
(12).蹲踞「つくばい」で手水をつかったら、茶席の出入り口へ進み、手がかりが切ってある戸 に 手をかけ開け、扇子を前において軽く頭を下げ、席中をうかがい、床、点前座の位置を見定め、にじって席に入り、草履の裏を合わせ、壁と沓脱石の間に立てかけ、席入りします。
床前に進み、掛物を拝見し、続いて茶道口近くの踏込み畳まで進んでから、道具畳に進み、器物の飾附と釜と爐とを拝見して、正客は次客以下の席入の妨げとならない場所(仮座)に着きます。
次客は、正客が仮座に着いたら、軽く一礼して、草履の裏を合わせ、壁と沓脱石の間に立てかけ、席入りします。
正客の作法を拝見し、正客の下座へ順に座ります。
お詰 は正客 が 床を 拝見し 立ち上がった時に、にじり入り、沓脱石の
上の自分の草履の向きを置き変え、出入り口の戸を軽く音をたてて
閉め、全員の席入りが終ったことを亭主に知らせます。
お詰 が床 を拝見し立ち上がったころ、正客は仮座から本来の座に着き、
次客以下同様にし、お詰は拝見が終わったら本座に着きます。
客一同が席に着くと、亭主が茶道口を開け挨拶に出ます。
挨拶が終わると、正客より掛物等について尋ね、掛物等についての問答が
あります。
席入りにはこのように決まったルール(お作法)があるんです。
お作法は お正客 とお詰め の 間のお席に着席し、茶道経験者の手順をまねて、
同じように所作、作法を行う事で、スムースにお作法を楽しく学べます。
炭点前
亭主が茶道口を開け、炭道具を持って出て、炭道具を炉の隣に置きつけます。
釜の鐶付に鐶を掛けて、釜を持ち上げ、釜敷の上に置き、羽箒で、炉縁と
炉壇の上を掃き清めます。
ここで、正客は挨拶をして、炉の近くに進み出ます。
次客以下も同様にして、客一同が炉を囲むような形で座り、炭点前の拝見をします。
亭主がぬれ灰をまき、羽箒で五徳の爪と炉縁と炉壇の上を掃き清めたあと、
炭をつぎます。炭がつぎ終わるとお詰から順に席に戻り正客だけが残ります。
亭主は(香合)を取り香を置きます。
正客は、亭主が香合の蓋をするころ、香合の拝見のあいさつをします。
亭主は、あいさつを受けて香合を出し釜の鐶付に鐶を掛けて、釜を持ち上げ、
五徳の上に置きます。
正客は釜が掛かったら香合を持って席に戻り畳の縁外、上座寄りに置きます。
正客から炭道具についてあいさつがあり亭主はそれに答えて炭道具を持って
茶道口から退出します。
亭主が茶道口を閉めると正客は上座に預かっていた香合を取り、香合を次客
との間に置いて挨拶をしてから膝前に取り拝見します。
次客以下も同様に拝見します。お詰の拝見が終わると、(香合)を持って立ち上がり、
道具畳近くで正客と出会い、正客に香合を返して席に戻ります。
正客は、もういちど確かめる気持ちで(香合)を拝見してから、香合を戻します。
亭主が、香合をとりに出たら、正客は礼を述べ席入り香合について
問答をします。
問答が終わると、亭主は香合を持って、茶道口に帰ります。
中立
客人が菓子を頂き、お詰(末客)が菓子器を給仕口へ返すと、正客は床前へ進み
床を拝見し次は道具畳に進み、名残の拝見をしてから出入り口を開けて、自分の
立てかけて置いた履物を揃えて露路へ出ます。
次客以下も順に同様にし、お詰は席中に取り残されたものがないか
見て露路へ出ます、出入り口の戸を少し音のするように閉め切り、
亭主に退出したことを知らせます。
亭主は、出入り口の戸を閉めきる音を聞いて給仕口を開け、菓子器
を取り込み掛物を外し、釜の蓋をして、席中を掃き清め、花入を掛けて花を入れ、
水指や茶入を置き付け、釜の蓋を切ります。
客は腰掛に戻り円座を配り各自手洗いを済ませて休憩します。
亭主は準備が整ったら銅鑼を「大小大小中中大」と七点打ち、客に準備が
整ったことを知らせます。
この時亭主が銅鑼の代わりに迎えるときもあります。
銅鑼の余韻が聞えなくなると、客はいったん腰掛に戻り、正客から順に蹲踞に進み、
右手で柄杓に手水鉢の水をたっぷり汲み、柄杓半分の水で左手を清め、
持ちかえて残りの水で右手を清め、再び右手に柄杓を持ちかえ、水を汲み左手に水を受け、手に受けた水で口をすすぎ、最後に残った水を静かに柄杓を立て流しながら柄杓の柄を清め、元に戻します。
詰は客一同が腰掛から立つと、円座と煙草盆を元あったように戻し蹲踞を使う前に中門を閉めます。
蹲踞で手水をつかったら茶席の出入り口へ進み、手がかりが切ってある戸に手をかけ開け、扇子を前において軽く頭を下げ席中をうかがい、にじって席に入り、草履の裏を合わせ壁
と沓脱石の間に立てかけ、席入りします。
床前に進み(花入と花を)拝見し続いて茶道口近くの踏込み畳まで進んでから道具畳に進み、器物の飾附と釜と爐とを拝見して、正客は次客以下の席入の妨げとならない場所(仮座)に着きます。
次客は、正客が仮座に着いたら、軽く一礼してにじり入り、草履を同様に扱って
から座して正客に一礼し、正客の通り拝見し、正客の下座へ順々に座ります。
お詰(末客)は、先客が床を拝見し立ち上がったときににじり入り、沓脱石の上の
自分の草履の向きを置き変え、出入り口の戸を軽く音をたてて閉め、全員の席入りが
終ったことを亭主に知らせます。
亭主は、出入り口の戸を閉めきる音を聞いて、露地に下り、蹲踞の水を入れ替え、円座、
煙草盆を引き、窓の簾を外します。
11月~4月は「炉の季節」になり(風炉釜)から(炉釜)に切替えます。
炉で使う炭は、風炉用の(くぬぎ炭)よりサイズが大きく、使う炭の数も多くなります。
白枝炭は細い枝の白色の炭です。
まとめ
茶道の炭点前は初めての方は慣れるまで、難しく感じてしまうことが多くありますね、
炭の種類だけでも
1.胴炭(どうずみ)
2.丸管(まるくだ)
3.割管(わりくだ)
4.丸毬打(まるぎっちょ)
5.枝炭などがあります。
茶道は慣れがとても大事です。
慣れてしまいますと、あとは同じことの繰り返しなんです。
時代の流れで、炭を使う点前は徐々に少なくなりました。
「正式な茶事」以外は電熱器で応用することが多くなってきました。
炉の炭点前は拝見するだけで風情があります。
お炭点前を行うには炭屋さんが何時まで、炭屋として存続していけるか、
文化生活が発展していく現代、炭屋さんの維持が茶道の課題となってきました。