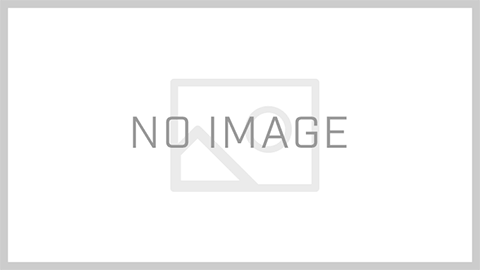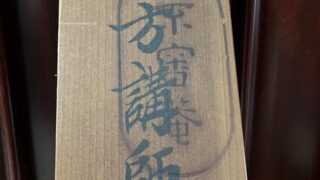Contents
表千家・ 裏千家 ・武者小路千家
茶道三千家の流派の違いと特徴
🔶ここでは(所作)や(点前)の違いを見ていきましょう。
茶道三千家は、各家元が独自の流派を築き上げ、表千家流不審庵千宗左、
裏千家今日庵千宗室、武者小路千家流官休庵千宗守について紹介します。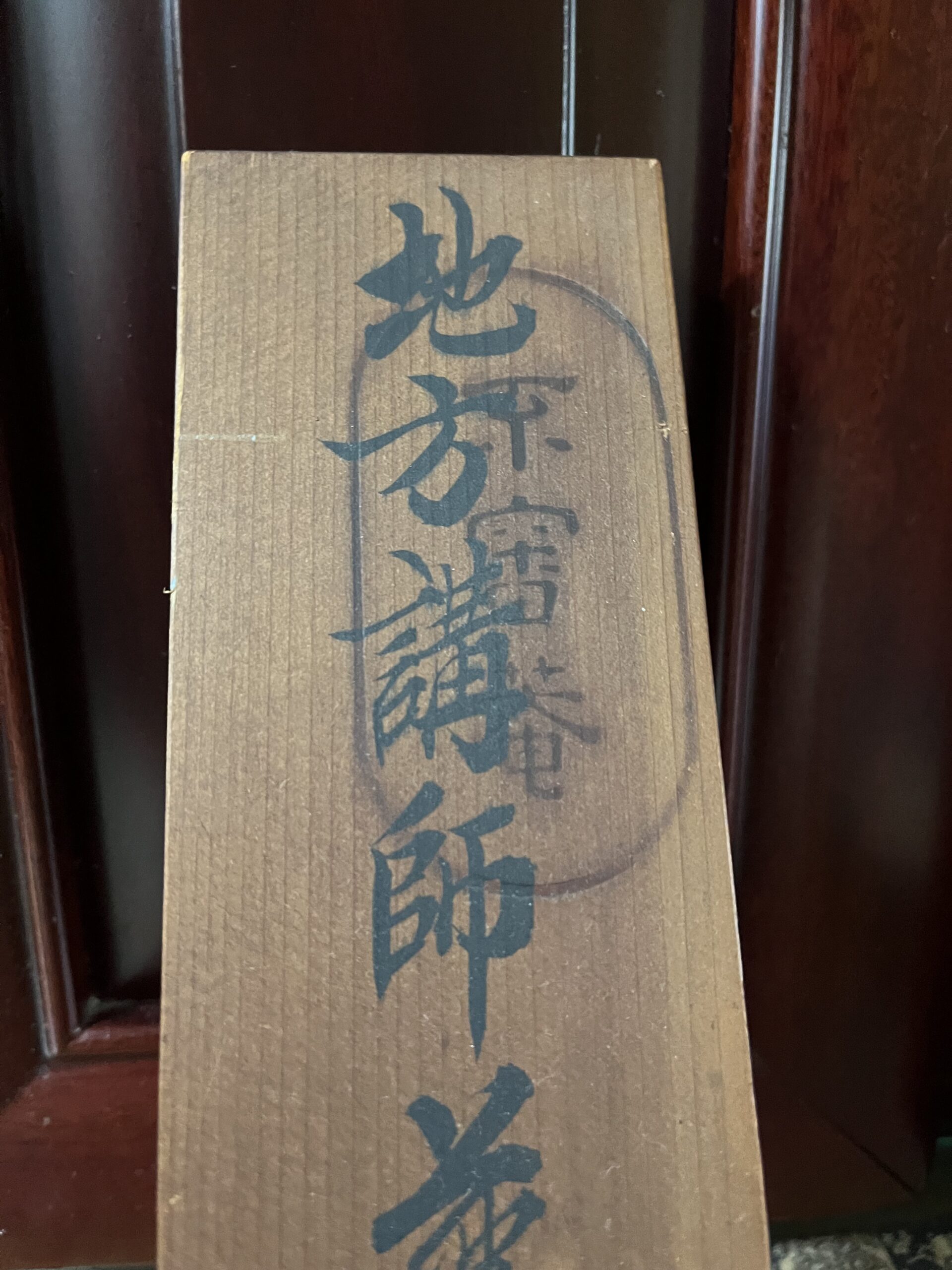
表千家は、千宗旦によって創始され、【千宗左】は不審庵を現在に至るまで、継承してきました。
表千家では、伝統を重んじ地味で落ち着いた茶席を好みます。
茶道界において最も広く一般に認知されている流派の一つです。
裏千家では、【千宗室】が今日庵を継承してきました。
武者小路千家は、【千宗守】が官休庵を継承してきました。
茶道の三千家 は 利休の祖先が数百年継承してきた茶道の家元です。その子息の三人がそれぞれの基本、元は元伯宗旦の子息で3兄弟です。
使用する道具や所作に多くの共通点を見ることができますが、作法や所作は微妙に異なります。
茶道流派武家
点前と所作の違い 武者小路千家
元伯宗旦の次男は官休庵を武者小路千家、千宗守が継承してきました。点前は抹茶は泡立てないのが原則です。ここは表千家と同じですね。
所作は畳の歩き方、柱側の足から茶室に入り、一畳を6歩で歩く、道具は帛紗、男性は紫、女性は朱色一色です。
武者小路千家は 侘び、さび を忠実に守り、何度か火事で、焼失しましたが立て直した経緯もあり侘び・さびの伝統を忠実に守ってきた流派です。ことさらに(伝統と合理性)を守ってきた武者小路千家です。
点前と所作の違い表千家
元伯宗旦の三男は「不審庵を表千家、千宗左」が継承してきました。
点前は抹茶は泡立てないのが原則です。
所作は畳の歩き方、左足から茶室に入り右足で出る、
一畳を6歩で歩く、道具は帛紗、男性は紫、女性は朱色が原則一色になります。
表千家流 は 古くからの作法を守っている 本格的で地味な流派です。
■ここに挙げたようにそれぞれの流派は茶道という一つの作法を守り、独自の所作を変化させていることに気付かれたことでしょう。
茶道は3千家をはじめ、数百という流派があります。
基本は変わってないことに茶道の奥深さがあります。
侘び や さび の基本茶道 を 広めた 千利休について深く知ることができます。
点前と所作の違い裏千家
宗旦の四男は今日庵を裏千家、【千宗室】を継承.
裏千家の『点前は抹茶は泡立てて、茶筅は手首を使います』
『所作は畳の歩き方、右足から茶室に入り、一畳を6歩で歩く、左足から退席します』
🔶畳の歩き方は右足から茶室に入りますが、🔶表千家とは反対の足から茶室に入る、
ココが違いますね。
お道具は帛紗、男性は紫、女性は赤色、柄物もあり種類は豊富です。
派手好みの裏千家です。
三千家の中でも、裏千家今日庵は伝統を守りつつ、時代に合った新しい棚物を考案するなど、お道具の種類も豊富なのが特徴です。
茶道三千家は元来親兄弟、作法やお道具に違いはありますが、お茶を点てて、客人におもてなしをする精神は三千家に共通しているのです。
このように、日本伝統文化茶道は、各流派ともに無駄なものは一切なく、利休独自の茶の湯の茶道は見事なほど合点のいく合理的 な作法となっています。
稽古をすればするほどその完結された作法のすばらしさを感じることができるでしょう。
500年を経た今も現代社会に於いても充分通用するお作法の数々、日常生活にも自然に取り込むことができます。
茶道文化は日本独自の和の心得を表す和敬清寂を利休の子息に継承して、一期一会も茶道の精神を余すところなく受け継ぎ、長い年月をかけ、今もその精神は生きています。
茶道 流派 京都
茶室の入り方と畳の歩き方
1.表千家:茶室に入るときは「左足から」畳1枚を「6歩」で歩く
茶室を出るときは「右足から」という原則です。
2.裏千家:茶室に入るときは「右足から」畳1枚を「5歩」で歩く
茶室を出るときは「左足」から出るのが原則になっています。
3.武者小路千家:柱側の足から1畳を6歩で歩くと定められており、右足左足という取り決めはなく茶室の造りによって変わります。
茶室を出るときの決まりはありません。
■ほかの流派とは異なっている作法がお分かりいただけると思います。
(武者小路千家独自の作法になっています)
大きな茶会では流派を問わず茶人が集います。
その時、足元を見ればどの流派でお稽古を重ねた人なのか一目瞭然です。
左足から茶室に入れば、表千家の流派です。
右足から茶室に入れば、裏千家流、柱付きの足から茶室に入
れば武者小路千家流なんです。
茶道は所作で流派が分かりますね。
茶会に必要な持ち物と服装
服装:茶会はフォーマルな場なので【着物は付け下げ】又は【無地】
訪問着は落ち着いた色合いの着物、黒留袖はNGです。
帯:袋帯又は名古屋帯が自然でふさわしいでしょう。
洋服:落ち着いた色のスーツ、ワンピーが良く、普段着ているお洋服でいいのです。
はじめての茶会は
お茶席には大きく分けて二種類あります。
1つ目は:【懐石、濃茶、薄茶】をもてなす正式な茶会である茶事です。
2つ目は:【大寄せの茶会】です。
多くの客を一同に招き 菓子と薄茶、濃茶、のみをもてなします。
初めてお茶を体験する方は、茶事に招かれることはないのですから、
🔶大寄せの茶会での作法を知っていれば大丈夫です。
ポイントは決められたルールがあります。
ルール=お正客とお詰目(末席)に座ってはならない決まりがあります。
ここを守れば気楽に茶の湯を楽しめますよ。
これだけ知っていれば大丈夫というのは、
次の四項目です。
持ち物では、最低限必要とする持ち物
1.扇子2.懐紙、3.楊子4.白足袋(茶室に入る前に履き替え用)
これだけ用意できれば茶会は安心、大丈夫です。
2.🔶正客と末客になってはいけない
正客とは、茶会における最上位の客のことで、一番上座に座り、客を代表して亭主と挨拶をかわし、問答するなど、正客として定められた作法もあり、茶道の技量のある人でないと勤まりません。
🔶ポイント:茶会では正客(上座)には座らない(決まり事。)
🔶末客は、お詰めといい、一番最後(下座)に座りお詰めの点前が必要とされる
役目なので、茶道の経験者又は茶会に慣れた人でないと勤まりません。
🔶ポイント:茶会ではお詰め(末席)に座ってはいけない。(決まり事)
ですから、初心者やはじめて茶会に招かれた客人は【正客と末客】に
なってはいけないんです。
■ポイント:理由は茶会を進めていく上のお作法を知っていなくてはスムーズに
茶会を進めていけないからです。
🔶大寄せ茶会では不特定の人が来ますので、お互いの経験を知りませんから、
遠慮しあって正客を譲り合いますので、はっきり『お茶会は初めて』なんですと
伝えましょう。さらに、正客の次に座る次客も避けましょう。
■ポイント:茶会が初めての方は両端の席はやめて、中間の席で茶の湯を楽しみましょう。
三. まわりの人の真似をする
真似をする! これ茶道ではとても大事なことなんです。
分からない時は左右の客人がすることをよく見て、同じ所作をすればいいんです。
しっかりと学んで、茶の湯を楽しみましょう。
扇子は茶室に入るとき、扇子を膝前に置きご挨拶、床の掛け軸の拝見の時には扇子を膝前に置き、両手をついてお軸を拝見します。
楊枝:お菓子を頂くときに懐紙と共に楊枝も必要になります。
懐紙の上でお茶菓子を楊枝で切って頂きます。
帛紗ばさみ:お道具をまとめて入れておく袋です。
白足袋・白靴下 (茶室を汚さない利休の心得から)茶室に入る前に
履き替えるための持ち物です。
履き替えようの白足袋、靴下は茶人の常識で常に茶室を汚さない気配りで
携帯しておきましょう。
これらが揃っていればお茶会で恥をかくことはありません。
茶の湯をゆっくり安心して楽しむことができます。
流派によっては、準備する持ち物に多少の違いはあります。
帛紗(ふくさ)
お茶のおもてなしをする亭主や半東は腰に帛紗をつけています。
客人の帛紗は帛紗入れにしまっておきます。
表千家の帛紗の色:男性は紫色で女性は朱色が原則
武者小路千家の帛紗の色:男性は紫色で女性は朱色が原則
裏千家の帛紗の色:男性は紫色で女性は赤色です。
裏千家ではこれに限らず、柄物も取り入れています。
『 裏千家では柄物の帛紗や、色も豊富です 』
裏千家を除く他の流派は帛紗は無地が原則です。
お辞儀
表千家:男性は両手を20cm位、女性は7~8cm位開けて八の字に手をつき、
横から見て30度くらい体を曲げてお辞儀をします。
裏千家:手のつき方は表千家と同じですが、お腹が膝に着くほど丁寧な「真」、前に体をかがめる位の「行」、手をついて軽くお辞儀をする程度の「草」の3種類に分けることができます。
武者小路千家:男女とも左手が前になるよう膝の前で軽く合わせてから 指先を膝前の畳に軽く付け、背筋を伸ばしてお辞儀をします。
座り方
表千家:正座をしたとき、男性は安定する広さに両膝を開け、女性はこぶし1個分位膝を開けて座ります。
裏千家:男性はこぶし2個分位膝を開けて座り、女性は表千家と同じようにこぶし1個分位膝を開けて座ります。
武者小路千家:表千家・裏千家に比べると膝の間隔が狭く、男性はこぶし1個分位、女性は膝を開けずに座ります。
菓子器と菓子鉢
主菓子器:菓子椀・菓子鉢・縁高・食籠の4種類の器
🔶菓子椀:
正式な茶会で主菓子を盛る際に用いられる菓子器です。
主に縁高や朱塗りのものが多く、吸い物椀と比較してやや背の低い器です。
蓋つきの器で、楊枝や黒文字を客数分添えて用意します。
🔶菓子鉢:主菓子を盛るための、陶磁製の器です。
唐物と和物があり、朱や金をあしらった絵が描かれているものが多く見られます。
🔶唐物:天竜寺青磁や七官青磁の端反鉢、輪花鉢、平鉢などがあります。
和物は透鉢を代表に、雪笹や雲錦鉢の手鉢などもあります。
菓子は客の人数分盛り、取り分け用の黒文字箸を1膳つけます。
🔶縁高:濃茶の際に用いる主菓子器です。
重箱の形の塗り物です。
🔶五重(5人分)で用意することが正式で、1段に1つずつ主菓子を盛ります。
客数が6人以上の場合は最上段に2つと菓子の数を増やし、それ以上の場合は
最上段から順に菓子の数を増やしていきます。
🔶どのような場合も最下段は必ず菓子の数を1つにします。
🔶蓋の上に人数分の黒文字を置き、正客から回します。
🔶食籠:菓子鉢や縁高同様に和菓子・主菓子を客の人数分だけ盛るために使用します。
🔶菓子鉢や縁高との大きな違いは蓋がついている点で、末客が最後に蓋を裏に返す必要があります。
🔶食籠は円形や角形のが一般的で、一段のものから重箱のように数段に分かれたものもあります。
🔶素材は漆器や陶磁器ですが、裏千家よりも表千家が好んで使用しています。
🔶干菓子器:水分の少ない乾燥した和菓子(干菓子)を入れるときに使用する器です。
代表的な菓子器には高坏・振出があります。
🔶高坏:皿や器に足のついた、背の高い器です。漆器に蒔絵の描かれたものから無地まで幅広く存在し、古くから伝わる器です。
🔶一般的に用いられる高坏は足の高さが5寸(15.2cm)以下のものです。
🔶振出:金平糖や霰、甘納豆などの小粒の菓子を入れるための菓子器です。
小型でひょうたん型のものが一般的です。
🔶口には菅で作られた栓があります。
🔶使用するときに振って菓子を出すことから振出の名がついています。
まず右手で振出を取って左手に持ち変え、次に菅の蓋を取り、一度懐紙の右上に置いてから両手で容器を回すようにして使います。
🔶🔶和菓子に欠かせないその他の道具:主菓子器や干菓子器の他、「黒文字」「銘々皿」も和菓子をふるまう際に欠かせません。
🔶黒文字:黒文字という名の木を削って作られた、楊枝の役割をするものです。
客が主菓子を食べる際に用いられます。
『用途によって長さが変わることが特徴の1つです。』
『菓子鉢や縁高に添えられる箸も黒文字の箸が一般的です。』
🔶銘々皿:銘々皿は、縁高を略した小皿ですが、菓子鉢や縁高とは異なり
客に対して一人ずつに分けて菓子を出すために用います。
🔶陶磁器や漆器、南鐐や砂張など数多くの種類があるため、場面や好みで
使い分けましょう。
🔶銘々皿は、客それぞれに同じ形のものを用い、楊枝か黒文字を1本ずつ添えて出します。
三千家が使う菓子器:
表千家:蓋つきで菓子が見えない菓子器を使用。
武者小路千家:蓋つきで菓子が見えない菓子器を使用。
裏千家:蓋がない菓子が見えるものを使用。
お菓子鉢は、正客から順に、次客、三客、お詰めと1つの菓子鉢にお菓子が入ってます。
菓子鉢がご自身の膝前に回ってきます。
菓子鉢から菓子1個を取り出し、自分の懐紙の上にのせます。
菓子器、菓子鉢はこのように用途によって使い分けをするのですね。
楊枝&楊枝入れ:楊枝はお菓子を頂くときに懐紙と共に楊枝も必要になります。
懐紙の上でお茶菓子を楊枝で切って頂きます。
帛紗ばさみはすべての道具をまとめて入れておく袋白足袋・白靴下(茶室を汚さない利休の心得から)、茶室に入る前に履き替えるための持ち物です。
これらが揃っていればお茶会で不便はありません。
茶の湯をゆっくり安心して楽しむことができます。
『野点』
茶室以外の場所、野で点てることから、野点と言います。
野点で使われる茶道具は、一式がコンパクトにまとめられ、持ち運びしやすいように『 野点用道具一式 』があります。
茶の湯は決まりがあって、難しいものと思われがちですが自然の中でもお茶を楽しむこともできるのです。
茶席以外、現代社会の日常生活に於いても自然に応用できる千利休の作法は無駄がなくそれぞれに納得がいくものになっていることをお稽古で感じました。
まとめ
茶道は決して小難しいものではなく、茶道のルールをしっかりと学び、
そのルールに従っていれば、お茶室のしつらいから、所作に至るまで
茶会をたのしむことができます。
お茶席が初めての方も、自然に茶室になじめる要素がたくさんあり、
お稽古初歩の方でも是非、日本茶道の奥深い魅力に触れてほしいと思いました。
所作のわずかな違いを重んじるのが三千家の作法です。
ご自分の流儀で、茶の湯を日常に取り入れてみてはいかがでしょうか。
。